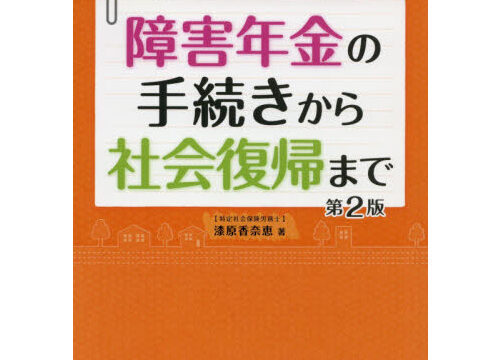日常生活や社会生活を送るうえで、ハンディキャップを感じることがありませんか。
とくに精神疾患の方は障害が目に見えないため、周囲の理解を得るのが難しいなど、ストレスを感じる場面も多いのではないでしょうか。
そんな精神疾患の方が周囲からの配慮を得て、自分のペースで就労できる働き方が「障害者雇用枠での就労」です。
今回は精神疾患を抱えながら、障害者雇用で働くことの課題とその対策についてここあらさんとお伝えします。
ここあらさんってだあれ?(ココをタップ♬)

就労移行支援事業所COCOCARAのキャラクターであり、Instagramでは様々な知識を教えているよ!
障害者雇用
身体障害、知的障害、精神障害などで障害者手帳をお持ちの方たちは、企業の障害者雇用枠を利用できます。
メリットの多い制度ですが、もちろんデメリットも存在します。
メリット・デメリットの両面を理解して、制度を利用することが重要です。
障害者雇用とは
厚生労働省の調査によると、令和6年は67万7,461.5人の障害を持つ方が、障害者雇用枠で働いています。
この数を多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれですが、前年比5.5%増加していることから、障害者の社会進出に大きな役割を担っていることは間違いないでしょう。
障害者雇用は障害者雇用促進法に基づいており、企業や公的機関は一定以上の割合(法定雇用率)で障害者の雇用を義務付けています。※
そのため企業や公的機関は、一般雇用とは別に障害者雇用枠での採用を行っているのです。
障害者雇用の対象者は、原則的に各自治体から発行される障害者手帳をお持ちの方に限られ、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の三種類があります。
(※現在の法定雇用率は民間企業2.5%、国や地方公共団体2.8%、都道府県などの教育委員会2.7%です。)
障害者雇用で働くメリットとデメリット
障害者雇用制度にデメリットがないわけではありません。
一般的なメリットとデメリットをまとめました。
【メリット】
・大きな企業は障害者雇用にも積極的な場合が多いため、優良企業への就職が有利
・心身両面での合理的配慮を受けながら、無理のない働き方ができる
・企業側にも税制上の優遇処置がある
【デメリット】
・障害を開示することに心的ストレスを感じる方もいる
・一般就労に比べて、障害者雇用の採用枠が少ない
・賃金が低い傾向にあり、キャリアアップが難しい

メリット・デメリット両方あるね
ご相談しませんか?
どのような精神疾患で障害者手帳を取得できる?
精神障害によって、日常生活や社会生活で長期間に渡り制約のある方が対象で、年齢や入院の有無による区別はありません。
すべての精神疾患の方が対象となっていて、2010年の障害者自立支援法改定により、発達障害も精神障害者保健福祉手帳の発行対象となりました。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、各市町村の窓口で申請します。
機能障害と能力障害の両面から審査が行われ、1級から3級まで等級が分かれています。
たとえば「脳卒中による片麻痺や視覚障害」という機能障害により、「箸が使えない。文字が見えにくい」などの能力障害が生じると、どれくらい生活が制限されるかを審査するのです。
【代表的な精神疾患】
・統合失調症
・うつ病や躁うつ病などの気分障害
・てんかん
・高次脳機能障害や認知症などの器質性精神障害
・ADHDやASD、LD、自閉症などの発達障害
・薬物依存症などの中毒精神病
・その他の精神疾患
参照:厚生労働省「障害者手帳」
参照:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」
ご相談しませんか?
精神疾患を抱える方が障害者雇用で働く課題と対策
現在、障害者雇用枠で就労する精神疾患の方は増加傾向にあります。
しかし職場定着率は決して高いとはいえないのが現状です。
就職後3カ月の定着率は精神障害の方が69.9%、発達障害の方は84.7%ですが、就職後1年では精神障害49.3%、発達障害71.5%まで低下します。
こうしたミスマッチを解消するために、様々な取り組みが必要となります。
障害者側の課題と対策
障害者側が感じる3つの問題点と、その対策をお伝えします。
(課題1)精神疾患の症状を安定させて就労することの難しさ
様々な症状や特性を抱える精神障害者にとって、安定して働き続けることは難しい場合もあります。
仕事中だけでなく通勤中にも、ハンディキャップを持つ障害者にとってはストレスを感じる場面は少なくないでしょう。
定期的に主治医や支援者と連携することで、就労可能な状況か判断することが重要です。
仕事を続けるには症状が酷くなる前に、通院や服薬を継続したり生活リズムを整えたりする必要があります。
通院や体調不良の際に休みやすいなど、勤務日数や勤務時間に融通がきくのは、障害者雇用枠での就労の大きなメリットです。
(課題2)周囲とのコミュニケーションが問題
精神的な疾患や障害を抱える方の中には、周囲とのコミュニケーションを苦手とする方もいます。
特性故に周囲に誤解され、人間関係で余計な軋轢を生んでしまっては、仕事を円滑に進めるのが難しくなります。
一緒に仕事をする同僚や上司に自分の障害を開示して、障害への理解を深めてもらうことで、社内のディスコミュニケーションを防げるのです。
(課題3)就労経験の少なさによるスキル不足
精神疾患や障害を持つ方の中には、就労経験が乏しく求められるスキルが足りない方もいます。
その様な場合は就労前に就労移行支援などで職業訓練を受けたり、基本的なビジネスマナーを学んだりすることがお勧めです。
就労支援制度を上手に利用し自分のスキルを磨くことで、就労のための準備ができます。
企業側の課題と対策
精神障害者の就職1年後の職場定着率は50%を切っており、障害者雇用の離職率の高さは企業にとっても頭の痛い問題です。
4つの問題解決の対策をお伝えします。
(課題1)社内の精神疾患や精神障害に対する理解不足・ノウハウ
精神の疾患は目に見えないため、「適切な対応が分からない」という声がよく聞かれます。
また同じ病名でも症状の現れ方が人によって異なることもあり、そうなると個別の配慮が必要になります。
しかし受け入れる側の上司や同僚の負担が大きくなり、周囲が疲弊しては、障害者雇用は進みません。
障害者と受け入れる社員たちの間にトラブルを生じさせないためにも、勉強会などを通じて社内で障害への理解を深める働きが必要です。
また会社として障害者雇用に取り組む意義や具体的な目標を、社員に丁寧に説明し理解してもらうことも重要でしょう。
こうして障害者雇用を進めて、ノウハウを蓄積していくことが、職場定着率を上げることに繋がるのです。
(課題2)障害にマッチした業務の切り出しの難しさ
症状の現れ方も異なるため、個々の適性に合った仕事を既存の業務から切り出すのに難しい場合もあります。
一般的な業務を切り出す方法としては、以下のようなステップがあります。
- 社内業務をすべて洗い出して業務内容をリストアップする
- リストアップした業務を障害者雇用された方ができる作業か否かで分類する
- 業務の手順や方法を明確にしてマニュアル化する
- 他の社員のサポート体制の下で障害者に業務を割り振り、業務に慣れてもらう
最初に実際の社内の全業務内容を、リストアップすることから始めます。
たとえば事務の仕事であれば「電話対応や備品の補充、書類整理、来客対応」などの業務を細分化することで、障害者に割り振れる業務があるか否かを判断します。
採用した障害者に切り出せそうな業務があれば、見える化とマニュアル化を進めて、障害があっても迷わず業務ができるようにします。
「書類整理」をマニュアル化するならば「書類のタイトル・日付・内容を確認」「書類を種類ごとに分ける」「定められたファイルの中に日付順に綴じる」「元の棚にファイルを戻す」といったマニュアルを作成する必要があります。
煩雑な作業と感じるかもしれませんが、障害者雇用に対応して業務の洗い出しを進めることで、企業内の効率化も図れるのです。
そして業務を切り出してからも適切なサポート体制が不可欠であり、定期的なフィードバックやいつでも相談できる環境づくりを構築します。
(課題3)他の社員への負担の増加・社内リソースの不足
障害者雇用を円滑に進めるためには業務窓口の一本化や、サポート体制を整えるなど、障害者が相談しやすい職場環境であることが大切です。
反面、「業務の遅延やトラブル」「突発的な業務の肩代わり」など、上司や同僚の負担が増している企業もあります。
突発的な問題に対応するには、余裕のある人員体制や業務設計の見直しが必要です。
障害者雇用には一定の人的リソースが割かれますが、人材の多様化が求められる今後の日本において、障害者が働きやすい職場体制の構築は企業全体としてもメリットがあるのではないでしょうか。
(課題4)採用時に適性や能力を正確に把握する難しさ
適切に業務を切り分けるためには、自社の業務内容と精神障害者の症状や特性がマッチしているかが問題です。
そのため障害者トライアル雇用の利用や、障害者就労をサポートする機関と連携して、できるだけ就労後のミスマッチが起きない採用活動が大切になります。

どちら側にも課題があるんだね
ここあらさんのひとこと
「配慮してほしいことと課題感があっているか
よく判断してみよう」

今回は精神疾患を抱える方が、障害者雇用で働く際の問題点やその対応お伝えしてきました。精神疾患の方は急な体調不良や、特性からの社会生活の難しさを感じることも少なくないでしょう。しかし適切なサポート体制があれば、自分らしく働くことが可能です。そのためには支援制度を有効活用することが重要になってきます。
私たち就労移行支援事業所COCOCARAでは、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。
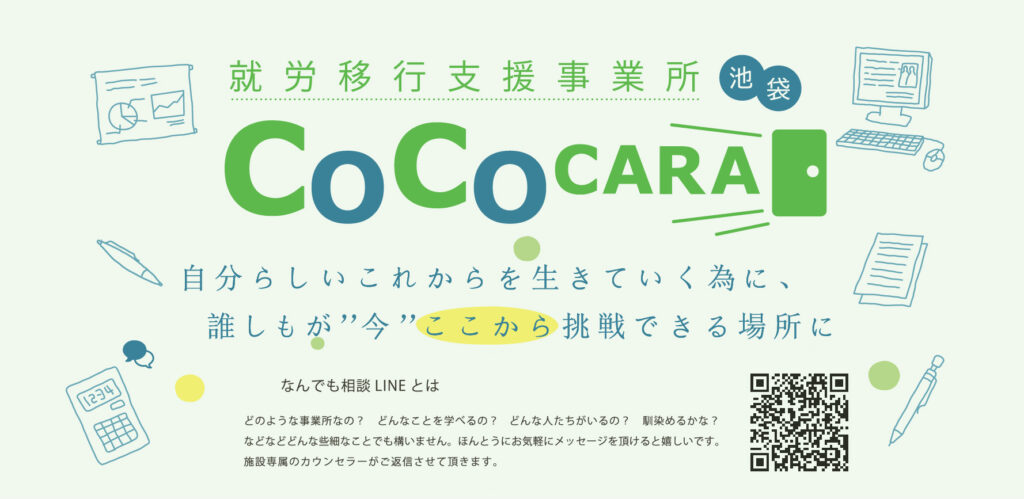
🐨見学・体験へのお申込み・相談
📩問合せ
📞電話
池袋オフィス 03-5980-8834
板橋オフィス 03-5944-1126
所沢オフィス 04-2941-4884
(電話受付時間 平日9時30分~18時)
💻ホームページ
https://cccara.com/
からもお気軽にご相談くださいませ!
DMからのご相談もお待ちしております♪
📓note
https://note.com/cococara_dayori
📌おすすめの記事
板橋区・北区で動画編集やWebデザインなどのITに特化した就労移行支援
#Webデザイン #動画編集 #htmlcss #就活 #うつ病 #発達障害 #適応障害 #hsp #豊島区 #就労移行支援 #池袋 #東武東上線 #都営三田線 #COCOCARA #障害者雇用 #板橋 #所沢 #所沢市 #所沢駅 #所沢駅すぐ #所沢駅近 #西武線 #新宿線 #池袋線 #ここあら
精神疾患でも働きたい!障害者雇用枠での働き方や課題!長く働くためのヒントも.jpg)