精神疾患や発達障害を抱えていると、「働くこと」や「職場に行くこと」に、大きな不安を感じる方も多いのではないでしょうか。治療は続けたいけれど、少しずつ社会に出る準備もしたい。
そんなときに選択肢のひとつになるのが「就労移行支援事業所」です。
中でも、精神科や心療内科と連携している事業所があることをご存じでしょうか?
「病院とつながっているなんて安心そう」と感じる一方で、「どんなメリットがあるの?」「注意点は?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
このブログでは、病院と連携している就労移行支援の特徴、メリットや注意点、こんな人に向いているという視点まで、ここあらさんとやさしく丁寧にお伝えします。
あなたの「安心して働く準備をしたい」という気持ちが、そっと後押しされる記事になればうれしいです。
ここあらさんってだあれ?(ココをタップ♬)

就労移行支援事業所COCOCARAのキャラクターであり、Instagramでは様々な知識を教えているよ!
就労移行支援ってどんな場所?

就職を目指すうえで、「今の体調でも働けるのか不安」「ブランクが長くて自信がない」などの悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に、精神疾患や発達障害などを抱えながら日々を過ごしている方にとって、「社会に出る」ことは決して簡単な一歩ではありません。
そんなときに頼りになるのが、就労移行支援事業所です。
これは、障害のある方(主に18歳〜65歳未満の方)を対象に、就職に向けた支援をおこなう福祉サービスのひとつです。
たとえば__
- ビジネスマナーやパソコンなどのスキル習得
- 就活の相談・面接練習
- 実習先や企業との橋渡し
- 体調管理や生活リズムの安定を一緒に考える
といったサポートを受けながら、自分のペースで就職準備を進めていくことができます。
そして最近では、「病院と連携している就労移行支援」を選ぶ方も増えてきました。
「通院しているけど、働く準備もしたい」という方にとって、医療とのつながりがある支援機関は、心強い存在になりうるのです。
今回は、そんな「病院と連携する就労移行支援」について、メリットと注意点の両面から、やさしく丁寧に解説していきます。
ご相談しませんか?
病院と支援機関が連携するとはどういうこと?
まず、「連携する」ってどういうこと?という疑問を持たれた方もいるかもしれません。
ここで言う“連携”とは、主に以下のような関係性を指します。
- 医療機関(精神科・心療内科)と情報を共有しながら支援を進めている
- 主治医の診断や意見書に基づいた支援計画が立てられている
- 医師と支援スタッフが相談・連絡を取り合える体制がある
- 病院の中に就労移行支援事業所が併設されている(※一部)
このように、就労支援の場と医療の場がつながることで、本人の体調や困りごとをより深く理解したうえで支援ができるのが特徴です。

知識のある方からの意見も聞けるね
精神科や心療内科とつながっている事業所の特徴

連携型の事業所には、いくつかのパターンがあります。
- 医療法人が運営しているタイプ
→ 病院やクリニックと同じ法人が就労移行を運営しており、医師や看護師との連携が取りやすい。 - 病院内または近隣に併設されているタイプ
→ 同じ建物やすぐ近くにあるため、通院と訓練をスムーズに両立しやすい。 - 医療機関と連携協定を結んでいるタイプ
→ 月に数回、医師との面談があったり、必要に応じて主治医に支援状況を報告したりできる。
もちろん、すべての事業所がこうした体制にあるわけではありません。
ただ、「医療とのつながり」があることで、いざというときの安心感がぐっと高まるのは確かです。
ご相談しませんか?
メリット・注意点
リワークとは?メリットやデメリットも-1.jpg)
【メリット①】主治医と連携しながら、安心して就職を目指せる
精神疾患や発達障害のある方にとって、「体調の波」はつきものです。
急に気分が落ち込んだり、過集中で疲れがどっと出たり、予期せぬ体調変化に戸惑うこともあるでしょう。
そんなとき、支援員が医師と情報を共有していると、
- 今の状態に合わせた支援スケジュールの調整
- 医師の診断をもとにした無理のない訓練内容の提案
- 訓練中に困っていることを主治医に伝えてもらえる
といった対応が可能になります。
「通院先にも、支援先にも同じことを何度も説明しなくていい」
「両方のスタッフが自分のことをわかってくれている」
この安心感は、就職までの道のりを大きく支えてくれるでしょう。
【メリット②】体調の変化に早く気づいてもらえる
連携している事業所では、体調の変化に気づいてもらいやすいという利点もあります。
たとえば、こんな小さなサイン__
- 以前よりも笑顔が減った
- 集中が続かない日が増えた
- 朝の通所が遅れがちになってきた
こうした変化を見逃さず、支援員が「最近の様子を主治医に共有してもいいですか?」と声をかけてくれるケースもあります。
利用者にとっても、「気づいてくれる人がいる」「誰かに見守ってもらえている」という感覚は、大きな安心材料になります。
【メリット③】主治医の意見が支援プランに反映されやすい
就労移行支援では、本人の希望や体調に合わせた「個別支援計画書」が作成されます。
この計画が、主治医の意見と連携して練られていると、より本人に合った支援になります。
- どのくらいの時間から通所を始めるか
- どんなストレスがあると調子を崩しやすいか
- 配慮してもらいたい特性や症状の特徴
こうした医師の知見を、支援計画にきちんと反映できるのは、連携型事業所ならではの強みです。
【メリット④】リワーク(復職支援)にもつながりやすい
「復職したいけれど、まだ体調が不安定」
「主治医に『もう少し安定してから』と言われたけど、どうしたらいいか分からない」
そんなとき、病院と連携している就労移行支援はリワーク(復職支援)にも強みを発揮します。
実際、医療機関の中にはリワークプログラムを持つところもあり、そこから就労移行へ段階的につなぐケースもあります。
両者がつながっていると、「医療から就労」までを切れ目なく支援できるのです。
【注意点①】すべての事業所が病院と連携しているわけではない
ここで注意したいのは、「連携している事業所」は限られているという点です。
就労移行支援には全国に多くの事業所がありますが、そのすべてが病院とつながっているわけではありません。
そのため、見学や体験に行く際には、
- 病院との連携があるか
- 通院中の医師と情報共有できる体制か
- 支援計画を医師に見せてくれるか
などを事前に確認することが大切です。
【注意点②】情報共有のタイミングや内容にはルールがある
病院と支援機関が連携している場合でも、「なんでもかんでも共有される」わけではありません。
基本的には、本人の同意があって初めて情報が共有されるというルールがあります。
- 医師に訓練中の様子を伝えてほしいとき
- 支援員に診断内容を参考にしてほしいとき
- 医療機関に現在の通所状況を報告してもらいたいとき
こうしたケースでも、事前に「この内容を伝えてもよいですか?」と確認されるのが一般的です。
そのため、支援員や医師と連携を希望する場合は、自分の希望や不安を伝えることがとても大切になります。
「主治医にこのことを伝えておいてもらえますか?」
「体調の波を記録して、支援計画に活かしてほしいです」
など、自分に合った連携方法を一緒に考えてもらいましょう。
【注意点③】医療に頼りすぎない“バランス”も大事
連携がしっかりしていることは大きな安心ですが、その一方で「すべてを医師に決めてもらわないと不安…」と感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、就労移行支援の主役はあくまで利用者自身です。
- 働きたい気持ちをどんな形で実現していくか
- 苦手なことをどう補うか
- 自分らしい働き方をどう作っていくか
こうしたことは、医師や支援員と一緒に考えつつも、自分の意志を軸にすることがとても大切です。
医療との連携を「サポートのひとつ」としてうまく活かしながら、自分のペースでステップアップしていきましょう。
【注意点④】合わないと感じたら“転所”も選択肢のひとつ
就労移行支援には、それぞれの事業所に特色があります。
医療との連携があっても、「支援スタイルが合わない」「雰囲気がしっくりこない」と感じることもあるでしょう。
そんなときは、「ここしかない」と思い詰めるのではなく、転所(別の事業所に移る)も視野に入れることが大切です。
たとえば__
- 病院とは連携していないけれど、サポートが丁寧な事業所
- 小規模で落ち着いた環境の事業所
- 就職後のフォローアップに力を入れている事業所
など、別の場所の方が自分に合っていることもあります。
就労移行支援は、「安心できる場所で、就職に向けて準備する」ことが目的です。
自分の心や体の声に耳をすませながら、無理のない環境を選びましょう。

注意点よく見てみよう
病院との連携が「安心して前を向く力」になることも
精神疾患や発達障害を抱えながら働くことは、決して簡単なことではありません。
でも、自分に合った支援や環境と出会えたとき、「自分にもできるかもしれない」と少しずつ希望が見えてくることがあります。
病院と連携する就労移行支援は、その“安心の土台”になってくれることもあります。
主治医とつながった支援スタッフが、「今のあなた」に寄り添いながら、無理のないステップを一緒に考えてくれる。
そんな環境があることで、「働くことが怖い」から「準備してみようかな」へと、気持ちが変わっていくのです。
もちろん、どんな支援が合うかは人それぞれです。
まずは、いくつかの事業所を見学してみる、支援員や医師に相談してみる――
そんな小さな一歩から、「自分に合った働き方」を見つけていけたら素敵だなと思います。
焦らず、比べず、自分のペースで。
あなたが安心して前を向けるような支援との出会いがありますように。
ここあらさんからのアドバイス
「メリットもあれば注意点もあるよ
どちらが自身にとって良いかを考えてみよう」

今回は就労移行支援事業所と連携している精神科・心療内科についてお伝えしてきました。「病院と連携している就労移行支援って、ちょっと安心できるかも」そんなふうに感じていただけたなら、この文章を書いた意味があるように思います。
就職を目指す道のりには、不安や体調の波、思うように進まない日もきっとあるでしょう。
でも、信頼できる医師や支援者とつながりながら、ひとつずつ自分の歩幅で進んでいけることは、心強い支えになります。
連携しているからこそ得られる安心。でも、それだけに頼らず、「今の自分にとってどういう支援が心地よいか」を大切にしてほしいと思います。
あなたが少しずつ前に進むとき、そっと寄り添ってくれる支援との出会いがありますように。そして、「働くって、こんなふうでもいいんだ」と思える未来が、あなたのペースで開けていきますように。
私たち就労移行支援事業所COCOCARAでは、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。
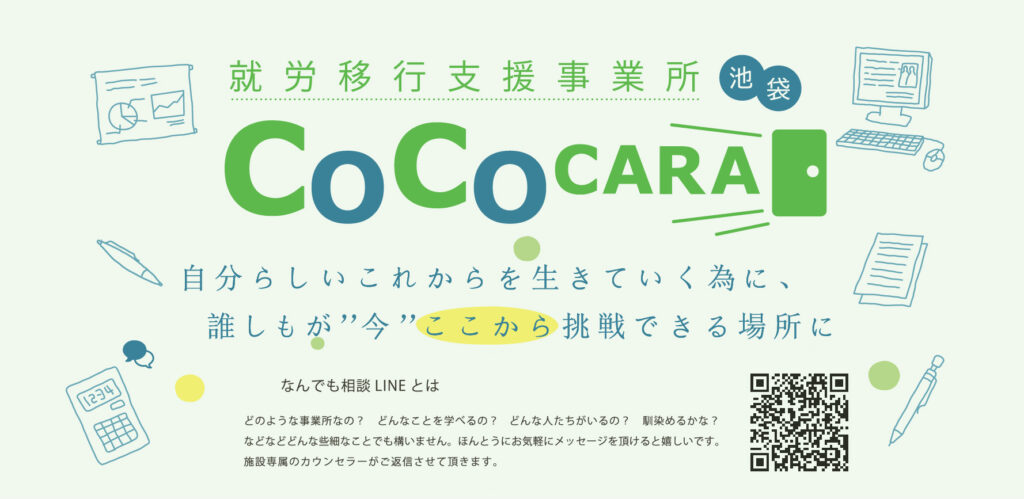
🐨見学・体験へのお申込み・相談
📩問合せ
📞電話
池袋オフィス 03-5980-8834
板橋オフィス 03-5944-1126
所沢オフィス 04-2941-4884
(電話受付時間 平日9時30分~18時)
💻ホームページ
https://cccara.com/
からもお気軽にご相談くださいませ!
DMからのご相談もお待ちしております♪
📓note
https://note.com/cococara_dayori
📌おすすめの記事
板橋区・北区で動画編集やWebデザインなどのITに特化した就労移行支援
#Webデザイン #動画編集 #htmlcss #就活 #うつ病 #発達障害 #適応障害 #hsp #豊島区 #就労移行支援 #池袋 #東武東上線 #都営三田線 #COCOCARA #障害者雇用 #板橋 #所沢 #所沢市 #所沢駅 #所沢駅すぐ #所沢駅近 #西武線 #新宿線 #池袋線 #ここあら















