障害がある方が働くうえで、「オープン就労(障害を開示して働く)」と「クローズ就労(障害を開示しないで働く)」という二つの選択肢があることは、すでにご存じの方も多いかもしれません。けれど、そのどちらかを選ぶことに不安や迷いがある方も多いのではないでしょうか。
「オープンにしたら偏見を持たれないか不安……」
「クローズにしたけど、配慮が受けられず働くのがつらい……」
「そもそも、自分の障害を職場にどう伝えていいか分からない……」
そんなときに、もうひとつの選択肢として知っておいていただきたいのが、「セミオープン就労」という考え方です。
この記事では、セミオープン就労の意味やメリット・デメリット、実際の支援現場での活用例、さらに当事者の体験談も交えながら、就職を考えている皆さまが自分にとって納得できる働き方を見つけるヒントをここあらさんとお伝えしていきます。
ここあらさんってだあれ?(ココをタップ♬)

就労移行支援事業所COCOCARAのキャラクターであり、Instagramでは様々な知識を教えているよ!
セミオープン就労とは?“一部にだけ開示”するという選択

セミオープン就労とは、簡単に言えば「障害のことを会社の全員に伝えるのではなく、必要な人にだけ伝えて働く」というスタイルです。
たとえば__
- 採用担当者や直属の上司には障害のことを伝えるが、同僚や他部署には伏せる
- 就労支援機関を通じて応募し、採用時に配慮事項のみ伝える
- 日々の仕事で必要な支援を受けつつ、周囲には一般的な社員と同じように接してもらう
など、ケースバイケースで柔軟に開示範囲を調整する働き方がセミオープン就労です。
この選択肢は、オープン就労とクローズ就労の“中間”に位置づけられるもので、「開示することで得られる支援」と「クローズにすることで守れるプライバシー」の、どちらも大切にしたい方にとって、有効な選択肢となります。
なぜ「セミオープン」という選択が必要なのか?
近年では、障害者雇用枠の活用が進んでいる一方で、「一般枠で働きたいけれど、支援や配慮も必要」という声も増えてきています。就労移行支援事業所などに通っている利用者さんのなかには、次のようなお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。
- 「配慮を受けたいけど、“特別扱い”と思われたくない」
- 「過去にオープンにしたら偏見や差別を受けた経験がある」
- 「働く力はあるけど、体調が不安定になるときもある。そんなときだけサポートしてほしい」
こうした思いに対して、就労支援の現場では、「完全なオープン・クローズの二択」ではなく、その人に合った形で開示を調整する“セミオープン”という考え方を提案することがあります。
働き方も、伝え方も、多様性があっていい。
セミオープン就労は、まさにそうした「自分らしく働く」ための新しい道なのです。

部分的なサポートが受けられるね
ご相談しませんか?
セミオープン就労のメリット
リワークとは?メリットやデメリットも.jpg)
ここからは、セミオープン就労の具体的なメリットについて見ていきましょう。
1. 必要な配慮だけを受けられる
セミオープンにすることで、自分にとって必要な範囲で職場の配慮を受けることができます。
たとえば__
- 通院のための勤務調整
- 作業のペースや指示の出し方への配慮
- 苦手な業務への柔軟な対応
など、特定の場面でだけ支援が必要な場合には、全社員に公表しなくても適切なサポートを受けやすくなります。
2. プライバシーを守りやすい
障害についてすべてを開示することに不安を感じる方も多くいらっしゃいます。セミオープンなら、最小限の開示で済むため、自分のプライバシーや安心感を保ちながら働くことができます。
3. 周囲との関係性が自然になりやすい
オープン就労にすると、「障害者だから…」と特別な目で見られることもありますが、セミオープンにすることで、必要な人以外には“あえて伝えない”というスタンスが、自然な人間関係づくりにもつながることがあります。
セミオープン就労のデメリットと注意点
前の章ではセミオープン就労のメリットについてご紹介しましたが、当然ながら「良いことばかり」ではありません。就労のスタイルとして選択する際には、次のようなデメリットや注意点にも目を向けておく必要があります。
1. 情報共有のバランスが難しい
「どこまで話すか」「誰に伝えるか」は非常に繊細な問題です。たとえば、直属の上司が理解していても、実際に日常的に関わる現場の先輩が何も知らないと、支援や配慮が途切れてしまうこともあります。
また、情報の伝え方にズレがあると、「本人から聞いていない」「支援者が勝手に伝えた」などの不信感が生まれることも。支援者・本人・企業の三者間で、丁寧な連携と調整が必要になります。
2. 周囲からの理解が得られにくいことがある
障害のことを全く知らない同僚からすると、「なぜあの人だけ休憩が長いの?」「なぜこの業務はしなくていいの?」と感じることがあるかもしれません。セミオープンの場合、その背景を説明しづらいという難しさがあります。
このようなケースでは、本人が直接伝えなくても、上司が「多様な働き方を支える方針です」といった形でチームに周知することで、ある程度の理解を得られる場合もあります。
3. 精神的な負担がかかる場合も
セミオープン就労は、自分の障害について“ある程度隠しながら働く”スタイルでもあります。人によっては「秘密を持っているようで苦しい」「もっと正直に言いたいのに言えない」といった葛藤を抱えてしまうこともあります。
また、症状が急に悪化したときに、開示していない人には状況をうまく伝えられず、サポートが届きにくくなることもあります。

メリットとデメリット、どちらの要素が多いと感じる?
ご相談しませんか?
支援者の視点で見た「セミオープン就労が向いている人」

就労支援の現場では、利用者さんの特性や希望に合わせて、どの就労スタイルが合っているかを一緒に考えることがあります。そのなかで、「セミオープン就労が向いていそう」と感じるのは、たとえば以下のような方です。
◆ 体調は安定しているが、時々サポートが必要な方
基本的には通常業務がこなせるものの、「繁忙期は疲れやすい」「生活リズムが乱れると不調が出やすい」など、特定の条件下で困りごとが出る方には、セミオープンが合う場合があります。
◆ 職場に“障害者雇用”という枠がない職場を希望する方
「特別扱いされたくない」「職務内容は一般雇用と変わらない形で働きたい」など、自分の能力を職場で評価されたいという希望を持っている方にも、セミオープンという選択は有効です。
◆ 他者との距離感を慎重に取りたい方
人間関係に不安がある場合や、過去に職場での偏見を経験してきた方にとって、セミオープンは自分の安心を守る一つの方法でもあります。
【体験談】実際にセミオープンで働いている人の声
ここで、実際にセミオープンで働いているAさん(30代・発達障害)の体験をご紹介します。
Aさんの声
新卒で入った会社では障害を隠して働いていましたが、コミュニケーションのずれや業務のミスが重なり、数ヶ月で退職しました。その後、就労移行支援を通じて就職活動を再スタート。「全部オープンにしなくてもいい」というセミオープンの選択肢を知って、今の職場では上司だけに特性を伝えています。
上司は「報連相の頻度」や「メモを残す文化」などでサポートしてくれて、業務も安定。同僚には詳しく話していませんが、「忙しいときはちょっと遅くなるかもしれません」くらいの会話はしています。
気を張りすぎず、でも支えてもらえる距離感が自分に合っていて、今はとても働きやすいです。
セミオープン就労を実現するために必要な準備とは?
セミオープン就労を希望する場合、いくつかの準備や工夫が求められます。
◆ 1. 自分の困りごとと必要な配慮を整理する
- どんな場面で困るか
- どんなサポートがあれば働けるか
- 逆に、どこまでなら周囲に伝えなくても大丈夫か
これらを整理することで、開示する範囲や伝え方の軸がはっきりしてきます。
◆ 2. 支援者と一緒に企業との調整をする
就労移行支援などのサービスを利用していれば、企業との橋渡しを支援者が担ってくれる場合があります。支援者が面接や面談に同席することで、「言いにくいことを代弁してもらえる」「配慮の相談がしやすくなる」などの安心材料にもなります。
◆ 3. 採用後の“見えない課題”に備える
たとえば、配慮がうまく伝わっていない、周囲との距離感がつかめない、といった場合には、アフターフォローの支援(定着支援)を活用するのも大切です。

必要な配慮まとめておこう!
あなたの働き方に、正解はひとつじゃない

障害のある方にとって、就職は単に「働く場所を見つける」ことではありません。
「どう生きていきたいか」
「どんな距離感で人と関わりたいか」
「何を大切にしながら働きたいか」
そうした、あなた自身の希望や安心感がとても大切です。
オープンでも、クローズでも、そしてセミオープンでも。
どれが“正解”ということはありません。
大切なのは、「いまの自分に合ったスタイルはどれだろう?」と、一度立ち止まって考えてみること。
そして、必要があれば、支援者や専門家に相談してみることです。
セミオープン就労という働き方が、あなたにとって「無理せず、自分らしく働ける道」につながる選択肢のひとつになれば嬉しく思います。
ここあらさんからのアドバイス
「自分らしく働けることを一番に考えよう
そのための方法はいくらでもあること忘れないで」

今回はセミオープン就労についてお伝えしてきました。障害を開示するかどうか。それはとても繊細で、簡単には答えを出せないテーマです。
「全部を伝えるのは不安だけれど、ひとりで抱えるのもつらい」
「特別扱いはされたくないけれど、困ったときには助けてほしい」
そんな気持ちを抱えている方にとって、“セミオープン就労”はちょうどよい選択肢になり得ます。
「こんな働き方もあるんだ」
そう知ることが、これからの選択肢を広げるきっかけになりますように。
私たち就労移行支援事業所COCOCARAでは、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。
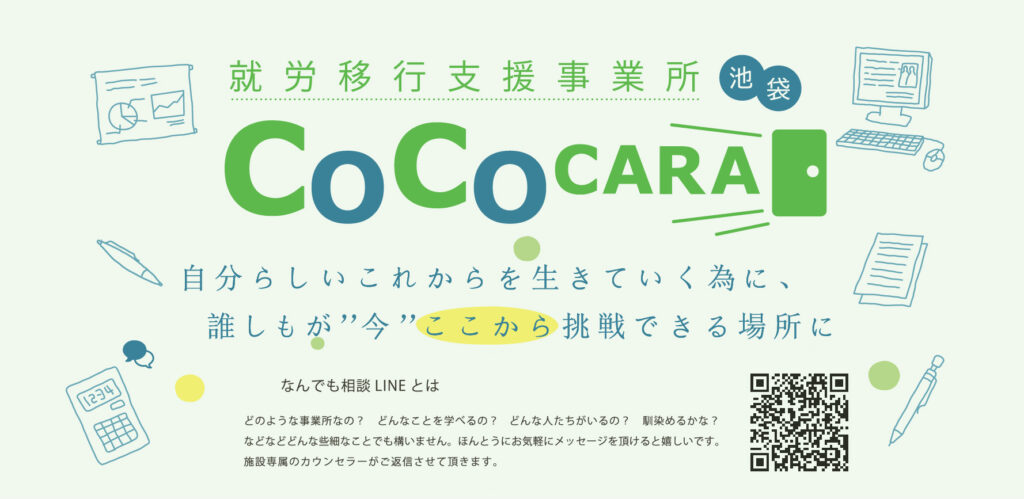
🐨見学・体験へのお申込み・相談
📩問合せ
📞電話
池袋オフィス 03-5980-8834
板橋オフィス 03-5944-1126
所沢オフィス 04-2941-4884
(電話受付時間 平日9時30分~18時)
💻ホームページ
https://cccara.com/
からもお気軽にご相談くださいませ!
DMからのご相談もお待ちしております♪
📓note
https://note.com/cococara_dayori
📌おすすめの記事
板橋区・北区で動画編集やWebデザインなどのITに特化した就労移行支援
#Webデザイン #動画編集 #htmlcss #就活 #うつ病 #発達障害 #適応障害 #hsp #豊島区 #就労移行支援 #池袋 #東武東上線 #都営三田線 #COCOCARA #障害者雇用 #板橋 #所沢 #所沢市 #所沢駅 #所沢駅すぐ #所沢駅近 #西武線 #新宿線 #池袋線 #ここあら板橋 #所沢 #所沢市 #所沢駅 #所沢駅すぐ #所沢駅近 #西武線 #新宿線 #池袋線 #ここあら
大人の学習障害(LD/SLD)とは?困りごとには便利グッズを活用!.jpg)














